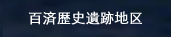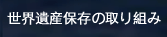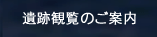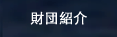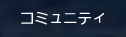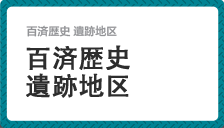羅城
羅城 は、首都を防衛するために築かれた外郭で、原形をよく保っている。扶蘇山城を起点として、扶余の北と東を囲んでいる。また、防衛のほかに、首都の中と外を分ける境界という性格を併せ持っていた。

扶余の西と南は錦江が自然の防御施設として機能し、自然堤防が城壁の役割を果たした。しかし、東は山地の間に平地が点在しているため、防御壁をつくる必要があった。羅城は、考古学的調査で総延長6.3㎞の区間が確認された。北羅城と東羅城から成り、北羅城は、扶余の北端に位置する扶蘇山城を起点に、東にある青山城の外郭を廻って石木里まで延びている。一方、東羅城は、石木里から塩倉里までである。北羅城は、百済滅亡後にその機能を失い、現在城壁が確認できる区間は多くない。しかし、今後考古学的調査が進んで地下に埋まっている城壁が確認されれば、全体の姿を解明できるものと考えられる。東羅城は現在も原形をとどめており、20年以上にわたる考古学的調査によって築造時期や築造技法、門址をはじめとする各種施設など全体像を把握できるようになった。
羅城は、ほかの山城とは異なり、山地と平地を結んで首都の外郭を取り囲む形になっている。また、ところどころ独特な築城法を採用しており、丘陵区間と低湿な平地の区間は異なる築城法を用いていたことが確認された。
まず、丘陵の区間は、城壁の内側で土を突き固めて盛り土をした後、城壁の外側は山を削って急斜面にし、石を2mほど積み上げて防御力を高めてある。一方、低湿地になっている区間は、枝葉敷設工法や、木杭を打ち込んで脆い地盤を補強する工法など、特殊な技術が利用された。まず、整った基盤土の上に直径5~6㎝の木と細い枝を城郭の底部の外郭線に沿って並べて敷き、基盤土層とその上に盛る土築層の間を遮断することで基盤層の安定を図った。木の枝を敷いた上には、粘質土を厚さ50㎝ほどに盛って枝を敷く過程を繰り返した。現在、これが3回繰り返されていたのが確認されており、枝葉敷設層と盛土層を交互に積み上げた高さが2mほど残存し、その規模を推測することができる。
また、城壁の内側と外側の縁に、間隔をとって木杭を打ち込んだ跡が確認された。杭の直径は5~10㎝、杭と杭の間隔は50~100㎝で、杭の根元が、基盤土層の上に木と細い枝を敷いた最初の層の上にまで達している。水分によって盛土層がその下の層と強く結合するようにするとともに、城壁の外側が崩れるのを防止するために、新しい工法を採用した例である。
低湿地の区間でもう一つ異なるのは、基礎部の外側に石列や積石層などの補強施設があるという点である。

扶余地域は、北・西・南の三方が錦江に囲まれている。このような自然条件のため、羅城の正門は東につくられた。正門にあたる第1東門址は、陵山里王陵のそばの平地で発見された。城門の幅は9.5mで、長方形の石材が使われている。
一方、2013年に行われた考古学的調査では、第2東門址が見つかった。第2東門址は、第1東門址から北に800m離れた峰に沿って北へ延びる扶余羅城が、北西方面に湾曲した場所に位置している。ここは標高120mの低い山の頂上部で、扶余市内はもちろん、益山の弥勒山まで見渡すことができる。
発掘によって確認された門址遺構からは、大量の瓦片や柱穴が見つかった。そのことから、門楼などの建物があったものと推定される。