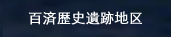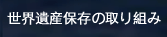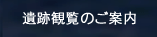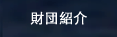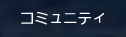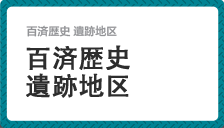時代別の遺跡
百済は、紀元前18年から660年まで約700年間存続した韓国の古代国家である。建国当初は漢江下流流域の小国だったが、朝鮮半島西南部地域を統合する中央集権的古代国家に発展した。百済は二度にわたって都を遷しており、首都の所在地によって漢城時代、熊津時代、泗沘時代に区分される。また、漢城時代を前期、熊津・泗沘時代を後期と区分することができる。漢城は今のソウル、熊津は忠清南道公州、泗沘は忠清南道扶余に当たる。
世界遺産に登録されたのは、百済後期の首都関連遺跡、つまり、熊津・泗沘時代の遺跡である。時期的には475年から660年まで(5~7世紀)の約200年に当たる。百済を含む東アジアの伝統的な都市は、統治と管理の機能を果たすために誕生した。このような東アジアの首都は、一国の政治・経済・宗教の中心地であり、その国の水準を示す文化の結晶といえる。
古代の東アジアの首都における様々な施設のうちとりわけ重要だと考えられたのは、王城と寺院、そして陵墓である。王城は王の統治空間と生活空間から成り、統治をしやすくするために複都(第二首都)を置くこともあった。寺院は首都の中または外に位置し、統治を宗教の面で正当化するとともに文化的共感を形成した。陵墓は首都の外側に隣接して立地し、前の時期の最高権力者であった先王と、現在の最高権力者である王をつなぎ、王室の正統性と神聖性を保障する空間であった。
世界遺産に登録されたのは、熊津時代の首都関連遺跡である公州の公山城と宋山里古墳群、泗沘時代の首都関連遺跡である扶余の扶蘇山城と官北里遺跡、羅城、定林寺址、陵山里古墳群、そして、泗沘時代後期に首都の機能を補完するためにつくられた複都関連遺跡である益山の王宮里遺跡と弥勒寺址である。これらの遺産を性格ごとに分類したのが以下の表である。
| 王宮 | 寺址 | 王陵 | 都市防衛の城 | |
|---|---|---|---|---|
| 熊津時代 (公州) |
公山城 | 宋山里古墳群 | ||
| 泗沘時代 (扶余) |
官北里遺跡と扶蘇山城 | 定林寺址 | 陵山里古墳群 | 扶余羅城 |
| 泗沘時代後期 (益山) |
王宮里遺跡 | 弥勒寺址 |
熊津時代(公州)の首都関連遺跡
475年に高句麗の攻撃を受けて首都の漢城が陥落すると、百済は戦争で廃虚と化した漢城から今の公州(ソウルから南に約130㎞)である熊津への遷都を断行した。公州に遷都する際に最も重視した立地条件は防衛の要素である。公州遷都は高句麗の侵入によって首都が陥落したために行われたもので、再び起き得る高句麗の侵入に備えることが急務だった。
公州地域は、錦江の中流に位置する菱形の盆地状の地形を呈している。東は鶏龍山が南北に広がっており、南と西も山に囲まれ、峠を通らずには公州に入ることが難しい。つまり、公州地域は、東・西・南は山地に囲まれており、北は錦江が東から西へ流れて敵の進路を遮っていて、防衛に有利であることに重点を置いた立地といえる。このような地形は、高句麗の侵入を防ぐという点で、百済が公州を新しい首都にする根拠となった。しかし、公州地域は、首都を支える経済的基盤や開放性などが乏しかったため、これらが後に扶余遷都を決める要因となった。
熊津地域は、今の公州市街地を横切る済民川によって東西に二分されている。済民川と錦江の合流地点は、洪水の際に浸水の危険がある低湿地であったため、公州市内で使用できる空間はごく限られていた。熊津時代の首都の範囲については、外郭城があったとする主張がかつて提起された。しかし、長期にわたる考古学的調査の結果、熊津時代には外郭城がなかったことが確認された。首都の範囲を推定する上では、陵墓の分布を参考にすることができる。陵墓の区域が首都の外側に配置される構造がはっきり現れるのは泗沘時代だが、そのような傾向は熊津時代にも存在した。公州市街地周辺の陵墓群としては、東に金鶴洞古墳群、西には宋山里古墳群などが配置されている。そのため、これらの古墳群の内側の範囲を当時の首都の範囲ととらえることができるだろう。
泗沘時代(扶余)の首都関連遺跡
百済は538年、今の扶余(公州から南西に約35㎞)にあたる泗沘へと二度目の遷都を断行した。その後、新羅・唐連合軍によって滅びる660年までの123年間にわたる泗沘時代の幕開けである。公州遷都の際に最も重視した立地条件である防衛の要素は、6世紀初頭高句麗との戦いで何度も勝利をおさめたという記録からもわかるように、あまり重要視されなくなった。扶余への遷都を断行した聖王(在位:523~554)は、先王である武寧王(在位:501~523)代の国家経営をさらに発展させるとともに、既得権を持つ貴族勢力を牽制することで王権を強化しようと遷都を決めたのである。公州盆地の面積は10㎢で、首都の立地には狭い地域だった。公州に比べて相対的に広い開豁地(扶余の面積は20㎢を上回る)があり、扶余地域の方が人口収容力が優っていたことも、遷都決定に影響したとみられる。さらに、扶余は満潮時に海水が到達するので、大型船舶が潮の干満だけで行き来することができる。この点は、物資の流通や文物の交流という側面で大きな利点となる。
だからといって扶余が防衛に脆弱な自然地形だったわけではない。扶余の北・西・南には錦江が曲線を描きながら流れ、自然の防御壁として機能している。東には、急峻ではないものの、補助的な防御施設を設置することで首都の防衛力を最大化できる標高200m前後の山々が連なっている。百済は、扶余の東方面の防衛力を高めるために、首都の外郭を廻らせた扶余羅城を築造した。
百済は公州の首都としての限界を克服するために、538年に扶余に都を遷した。扶余は、王宮と、平時には王宮の後苑であり有事の際には避難場所となる山城で構成された王城が、錦江に隣接する北部中央に位置し、王城を含む都市全体を外郭城である扶余羅城が囲む構造である。 扶余地域の首都関連遺跡である都城については、30年以上にわたる精密な考古学的調査が行われた。その結果、王宮とみられる大型建物址や首都内の寺院跡、羅城、陵墓など1500年前の百済の都の姿が明らかになりつつある。
泗沘時代(益山)の首都関連遺跡
百済の第30代の王である武王(在位:600~641)は益山(扶余から南に約50㎞)生まれと伝えられており、在位期間中、弥勒寺の創建など積極的な益山経営を試みたとされる。これは、扶余地域を中心にした貴族勢力を牽制することにより王権を強化するとともに、新羅との戦いなどにおいて戦略的拠点となる益山を通じて百済南方地域での掌握力を確保することなどを目的にしたものとみられる。錦江や萬頃江などの河川や海に近いため水上交通が発達しやすいという利点と、南方面の全州、任実、南原を結ぶ陸上交通の要衝という立地から、益山地域の戦略的重要性がわかる。益山やその周辺の論山、完州、金堤地域は、朝鮮半島で最も広い平野部に位置している。現在の高い農業生産力からすると、百済時代もこの地域はほかに比べてはるかに農業が盛んであったと推測されており、こうした経済的な理由も益山を複都とする背景となったものとみられる。武王が益山を重視したことを示す証拠は、王宮里遺跡や弥勒寺址などに表れている。百済後期の主要な遺跡は、弥勒山(標高430m)や龍華山の裾野(標高340m)
の南の扇状地や低い丘陵地帯などに点在しているが、このような地理的、歴史文化的環境は、益山地域に泗沘時代の首都機能を補完する複都がつくられるための十分な要件となっている。